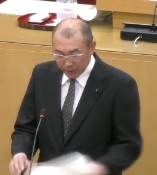|
8日に開会した9月定例県議会は16日、一般質問2日目(12日、16日、17日)に入り、最初に秋田北地方の児玉政明議員(鹿角・自民党)が登壇した。この中で同議員がかづの牛の輸出について質したところ、鈴木知事は出荷頭数の少なさなどを指摘した上で、まずは国内需要の拡大に向けて産地の取り組みをサポートしていくとの考えを示した。また、独自に医療ビジョンの策定に取り組む市町村に対する助言、指導の方向性を同議員が質したのに対し、知事は「県の医療構想と相互に調和の取れたものとなるよう情報共有を図るとともに、必要に応じて助言を行うなど積極的に協力していく」とした。かづの牛と地域医療に関する同議員の質問と答弁の要旨は下段のとおり。
<かづの牛の輸出> 今年1月、農水省のGI、地理的表示保護制度にかづの牛が登録された。全国の和牛では日本短角種として初めての制度登録で、申請元のかづの牛振興協議会をはじめ地元では喜びと今後の取り扱いに期待する声が高まっている。かづの牛については赤身肉のヘルシー志向の高級食材として、また、和牛の中の1%以下という希少価値の高さを売りにすることで一定の層への販路拡大が期待できる一方、生産頭数が少なく、輸出向けの数量の確保がむずかしいといった点もあることは承知しているが、知事はかづの牛の輸出についてどのように考えているのか。
<知事答弁> かづの牛は低カロリーな赤身肉が特長で、消費者の健康志向に沿った魅力のある牛肉であると私も高く評価しているが、輸出を目指すには出荷頭数が少ないことに加え、海外ではサシの入った和牛肉のニーズが一般的に高いといった課題がある。このため、まずは飼養戸数や頭数など生産基盤の強化を図るとともに、GI登録による地域ブランドの強みを生かし、国内での需要拡大に向け、認知度向上や販路拡大などの産地の取り組みをサポートしていく。
<地域医療> 鹿角市では、鹿角地域の医療の将来像について医療機関や住民と話しあい、関係者間で持続可能な目標をもつための医療ビジョンの策定を今年度から2年かけて進めるようだ。鹿角地域では、地域の中核病院の診療体制の縮小が続き、今後の地域医療の提供体制が大変注目されている。そこで(知事に)うかがいたい。新しい地域医療構想で目指す2次医療圏はどのようなものなのか、集約化一辺倒ではなく地域が真に必要な医療が残せるように地域での議論を積極的に行ってもらいたいがいかがか。また、鹿角市のように今後独自に医療ビジョンの策定に取り組む市町村に対してどのような助言や指導をしていくのか、知事の考えをうかがう。
<知事答弁> 2次医療圏の広域化は今後のさらなる人口減少や高齢化による医療ニーズの変化、医療従事者の不足や偏在を見据え、限られた医療資源を有効に活用し、持続可能な医療体制を構築していくことを目的に行ったものである。こうした医療圏の広域化において、医療機能を分担し、連携を進めることは決して医療を遠ざけるものではなく、むしろ必要な医療を地域に残し、バランスの取れた医療提供体制の構築を目指すものだ。現行の地域医療構想は入院医療を中心とした内容だったが、新たな構想は外来や在宅などの身近な医療を含めた地域医療全体のあり方を描くものであり、策定にあたっては今後示される国のガイドラインを踏まえつつ、地域医療構想調整会議等を通じて本県医療の目指す姿を共有し、幅広い関係者と十分に協議を重ねていく。
また、身近な医療から一般的な入院医療までを単独の市町村で完結することはむずかしく、2次医療圏単位で医療機能の分担と連携により支えていく必要があるものと考えている。このため、市町村が計画を策定する際には、県の医療構想と相互に調和の取れたものとなるよう情報共有を図るとともに、必要に応じて助言を行うなど積極的に協力していく。(午後2時)
※このページには広告を掲載しております。
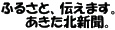 |